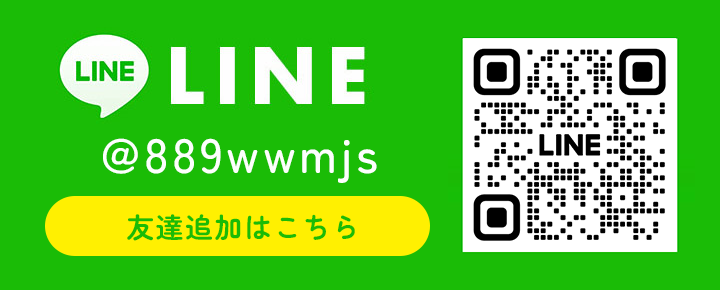難聴・耳鳴りで
お困りの方へ

耳の不調として多くみられるのが「難聴」と「耳鳴り」です。
どちらも日常生活の質(QOL)を大きく左右する症状であり、互いに関連して起こることも少なくありません。
当院では両方の症状に対して、正確な診断と適切な治療を行っています。
難聴とは
難聴は、音や声が聞こえにくくなる状態を指します。単に音量が小さく感じるだけでなく、言葉の聞き取りづらさや音の違いがわかりにくくなるなど、さまざまな形で現れます。年齢を問わず発症する可能性があり、突然起こる場合もあれば、徐々に進行していくこともあります。
難聴によって、家族や友人との会話がスムーズにいかない、電話での会話が困難、テレビの音量を上げる必要があるなど、日常生活に支障をきたすことがあります。京都市伏見区エリアにお住まいで「最近聞こえにくい」「会話がしづらい」と感じる方は、できるだけ早めの受診をおすすめします。
伏見ひまわりクリニックは、竹田駅、伏見駅から徒歩9分の場所にある耳鼻咽喉科です。
最新の検査機器と豊富な経験をもとに、あなたの難聴の原因を正確に診断し、適切な治療をご案内します。
難聴の種類と原因
難聴は大きく分けて「伝音難聴」「感音難聴」「混合性難聴」の3つに分類されます。
-
伝音難聴
伝音難聴は、外耳や中耳に問題があり、音が内耳まで十分に伝わらないことで起こります。
耳垢の詰まり、中耳炎、耳小骨の異常などが主な原因です。
多くの場合、適切な治療により改善が期待できます。 -
感音難聴
感音難聴は、内耳の蝸牛や聴神経に障害がある場合に生じます。
加齢性難聴(年齢によるもの)、騒音性難聴、突発性難聴、メニエール病などが原因となります。
また、特定の薬剤の副作用として起こることもあります。 -
混合性難聴
混合性難聴は、伝音難聴と感音難聴が併存している状態です。
長期間の中耳炎などにより、伝音系と感音系の両方に障害が及んだ場合などに見られます。
当院では、詳細な聴力検査を行い、難聴の種類と程度を正確に診断した上で、最適な治療法をご提案いたします。
難聴の程度
難聴の程度を正確に把握することは、最適な対応策を選択する上で重要な要素となります。
| 軽度難聴 聴力レベル:25dB以上-40dB未満 |
通常の会話は理解できますが、小さな声や遠くからの話しかけが聞き取りにくくなります。 グループでの会話や騒がしい環境では、言葉を聞き逃すことが増えていきます。 |
|---|---|
| 中等度難聴 聴力レベル:40dB以上-70dB未満 |
日常会話の聞き取りに支障をきたします。 声自体は認識できても、内容を正確に理解することが難しく、特に子音の区別がつきにくくなります。 |
| 高度難聴 聴力レベル:70dB以上-90dB未満 |
通常の話し声ではほとんど聞こえず、大きな声や補聴器の使用が必要になります。 会話には視覚的な手がかり(口の動きの読み取りなど)も重要になってきます。 |
| 重度難聴 聴力レベル:90dB以上 |
非常に大きな音(掃除機の音、バイクのエンジン音など)しか知覚できません。 補聴器を装用しても会話の理解は困難で、コミュニケーション方法の工夫が必要になることがあります。 人工内耳の適応を考えます。 |
難聴の治療
難聴は原因や症状の現れ方が多様なため、一人ひとりの状態を詳しく診断し、それに合わせた治療アプローチが必要になります。
当院では、難聴のタイプや程度に応じて様々な治療選択肢をご提案しています。
突発性難聴やメニエール病には薬物療法、滲出性中耳炎には鼓膜切開術、高度・重度の感音難聴には人工内耳手術、
また多くの難聴症例には補聴器による聴力補助などが考えられます。
さらに、難聴による心理的影響に対するサポートも重要な治療の一環です。
耳鳴りとは
耳鳴りとは、実際には音がしていないにもかかわらず「キーン」「ジー」といった音が聞こえる状態です。
なお、耳鳴りには以下の2種類があります。
| 自覚的耳鳴り | 患者さん本人にしか聞こえない、耳鳴りの大多数がこのタイプです。 耳鳴りの症状のおおよそ90%以上を占めます。 |
|---|---|
| 他覚的耳鳴り | 耳周辺の音(血流や筋肉の音)が原因で、医師が聴診器などで聴診できる耳鳴り。 非常に稀なタイプですが、動脈の血流音や筋肉の痙攣などが一般的な原因です。 |
耳鳴りの症状と原因
耳鳴りの主な症状としては、以下のような内容がよくみられます。
- 耳の圧迫感や痛みのあとに音が鳴るように感じる
- 静かな環境で特に耳鳴りが気になる
- ストレスや疲労、睡眠不足で耳鳴りが悪化する
- 音が気になって会話や仕事に集中できない
- 耳鳴りによって眠りに入りにくい、途中で目が覚める
そして、耳鳴りの原因は大きく2つに分けられます。
-
重篤な疾患によるもの
脳腫瘍や脳梗塞・脳血管疾患などが背景にあり、この場合は、CTやMRI/MRAによる精密検査が必要で、大学病院や脳神経外科などの専門機関をご紹介します。
-
耳や全身の病気に関連するもの
中耳炎や突発性難聴、加齢による難聴、内耳炎やメニエール病といった耳の疾患に伴うケースが多く、心臓・血管系など全身の病気が関係する場合もあります。特に全体の90%を占める「自覚的耳鳴り」は患者さん本人にしか聞こえず、難聴に伴って脳が不足した音を補おうとする過程で起こることが多いとされています。一方、血流音や筋肉の痙攣など身体の構造的な音が原因となる「他覚的耳鳴り」もあり、稀ですが医師が聴診器などで確認できる場合もあります。
耳鳴りの治療
耳鳴りは「完全になくす」ことが難しい症状ですが、適切な治療により生活に支障のない程度まで軽減し、不安を和らげることが目標となります。
当院では、次のような方法でサポートを行っています。
-
薬物療法(内服薬など)
耳鳴りの症状を和らげるために、血流を改善する薬や神経の働きを整える薬を使用します。
体質や症状に合わせて処方し、耳鳴りによる不快感の軽減を目指します。 -
補聴器治療とTRT療法(耳鳴り再訓練療法)
難聴を伴う耳鳴りの場合、補聴器を使用することで周囲の音が聞き取りやすくなり、相対的に耳鳴りが目立ちにくくなります。
さらに、補聴器を用いることで聴力低下による脳の過剰反応を抑える効果と、周囲の音によるマスキング効果の両方が期待できます。最近では、耳鳴り治療専用の機能を搭載した補聴器もあります。また、TRT療法(耳鳴り再訓練療法)では、補聴器や専用のサウンドジェネレーターからやさしい音を流し、「耳鳴りに慣れる」ことを目指します。耳鳴りを消すのではなく、日常生活で気にならない程度に意識から遠ざけることで、不快感を和らげ、心理的な負担を減らしていきます。
-
生活指導・カウンセリング
耳鳴りはストレスや生活習慣、自律神経とも深く関係しています。
睡眠の質を整える工夫やリラックス法の提案、心理的サポートを行い、患者さまが安心して生活できるようサポートします。
耳鳴りに悩まれている方へ「耳鳴りを消す」ことよりも「耳鳴りとうまく付き合う」ことが大切です。
一人で不安を抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

最後に
当院では、難聴と耳鳴りを切り離して考えるのではなく、両者を総合的に評価し、一人ひとりの症状や生活スタイルに応じた治療を行っています。
大切なのは早期発見と早期対応です。「最近聞き返すことが増えた」「テレビの音量が大きいと指摘される」といった変化を感じたら、京都市伏見区の耳鼻咽喉科、伏見ひまわりクリニックまでお気軽にご相談ください。
当院は竹田駅、伏見駅から徒歩9分の場所に位置し、丁寧な診察と最新の検査機器を用いて、あなたの聴力の状態を正確に把握し、最適な治療法をご案内いたします。