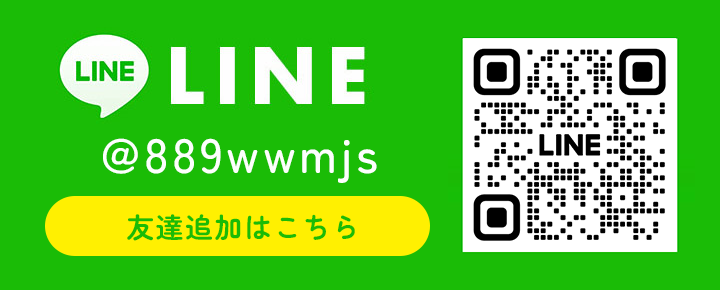めまいとは

めまいは、自分自身や周囲が回っている、揺れているように感じる症状を指します。めまいはあくまで症状であり、それ自体が単独の病気ではありません。めまいは、内耳の障害や脳の血流不全、さらには心理的なストレス要因など、さまざまな原因が背景にあります。めまいが生じると日常生活に大きな支障をきたし、立っていられなくなったり、吐き気を伴ったりすることもあります。特に高齢者では転倒のリスクが高まるため、適切な診断と治療が重要です。
めまいの症状が続く場合や繰り返し起こる場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。伏見ひまわりクリニックは京都市伏見区にある耳鼻咽喉科です。竹田駅・伏見駅からいずれも徒歩9分の立地で、通院のしやすさにも配慮しています。当院では最新の検査機器と専門知識を活かし、あなたのめまいの原因を特定し、適切な治療を提供します。
めまいの種類と原因
めまいは大きく分けて「回転性めまい」と「非回転性めまい」に分類されます。それぞれの特徴と主な原因疾患について説明します。
回転性めまい(ぐるぐる回る感覚)
自分や周囲が回っているように感じるめまいで、内耳の平衡感覚を司る器官(前庭)が関係しています。突然発症し、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。
| 代表疾患 | 特徴 |
|---|---|
| 良性発作性頭位めまい症(BPPV) | 頭の位置を変えたときに短時間の激しいめまいが起こります。耳石が三半規管に入り込むことで生じます。 |
| メニエール病 | めまいに加え、耳鳴り・難聴・耳閉感が繰り返し起こる疾患。内耳のリンパ液の異常が原因とされています。 |
| 前庭神経炎 | ウイルス感染などにより前庭神経が炎症を起こし、持続的な強いめまいが出現します。聴力は保たれることが多いです。 |
| 内耳炎 | 内耳の感染や炎症によって、めまいとともに難聴が起こることがあります。 |
浮動性めまい(ふわふわする感覚)
地に足がついていないような不安定感があり、歩行時にふらつくことが多いです。脳の血流障害や神経系の異常が関係することがあります。
| 代表疾患 | 特徴 |
|---|---|
| 脳梗塞・脳出血 | 小脳や脳幹の障害により、平衡感覚が乱れます。手足の麻痺や言語障害を伴うこともあります。 |
| 頸性めまい | 首の筋肉の緊張や頸椎の異常が原因で、血流が悪くなりめまいが生じます。肩こりや頭痛を伴うこともあります。 |
| 高血圧・低血圧 | 血圧の急激な変動により、脳への血流が不安定になり、ふらつきや立ちくらみが起こります。 |
| 貧血 | 酸素供給が不足することで、脳が一時的に虚血状態となり、めまいや倦怠感が現れます。 |
動揺性めまい(揺れているような感覚)
身体が揺れているように感じ、特に歩行時に不安定さが目立ちます。加齢や神経変性疾患が関係することが多いです。
| 代表疾患 | 特徴 |
|---|---|
| 小脳変性症 | 小脳の機能が徐々に低下し、バランス感覚が失われていきます。歩行障害や言語障害を伴うことがあります。 |
| パーキンソン病 | 筋肉のこわばりや動作の緩慢さに加え、姿勢保持が困難になり、ふらつきが生じます。 |
| 加齢性平衡障害 | 加齢に伴い、視覚・聴覚・筋力などの複合的な低下により、バランスが取りづらくなります。 |
失神に関連するめまい・ふらつき
| 代表疾患 | 特徴 |
|---|---|
| 神経調節性失神(血管迷走神経反射) | 立位や強い緊張・排尿・咳などで迷走神経が過剰に働き、血圧・脈拍が低下して意識消失やふらつきを起こす。 |
| 起立性低血圧 | 急に立ち上がった際に血圧が十分に保てず、脳血流が低下しふらつきや失神が生じる。 |
| 心原性失神 | 不整脈(洞不全症候群、房室ブロック、心室頻拍など)、大動脈弁狭窄症、肥大型心筋症などで、心拍出が急激に低下することで生じる。 |
| 脳血管性失神 | 椎骨脳底動脈系の一過性虚血発作(TIA)などで、めまいや意識消失を伴うことがある。 |
心因性めまい(精神的な要因によるめまい)
ストレスや不安など心理的な要因が背景にあり、検査では異常が見つからないことが多いです。慢性化しやすく、生活の質に影響を与えることがあります。
| 代表疾患 | 特徴 |
|---|---|
| 不安障害・パニック障害 | 強い不安や恐怖により、めまいや動悸、過呼吸などの症状が現れます。 |
| 自律神経失調症 | 自律神経のバランスが乱れることで、めまい・動悸・倦怠感など多様な症状が出現します。 |
慢性機能性めまい
| 代表疾患 | 特徴 |
|---|---|
| PPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい) | 軽度のめまいが持続し、姿勢や動作によって悪化します。過去のめまい発作がきっかけとなることがあります。 |
| 自律神経失調症 | 自律神経のバランスが乱れることで、めまい・動悸・倦怠感など多様な症状が出現します。 |
当院のめまい検査の体制
1.赤外線CCDカメラと電気眼振図
めまいの発作時には、目に特徴的な動きが現れることがあります。
当院のめまい検査では、肉眼では捉えにくい微細な眼球運動を正確に記録するために赤外線カメラ(CCDカメラ)による映像記録と、
電極を用いた電気眼振図(ENG)の両方を併用しています。
これにより、眼の動きを 「映像で見える形」と「数値で記録される形」の両面から確認でき、より正確な診断につながります。
2.聴力検査
内耳の異常はめまいと聴力低下を同時に引き起こすことがあります。
聴力検査を実施することで、メニエール病や突発性難聴など、耳の機能障害に起因するめまいかどうかを判断する手助けとなります。
3.重心動揺計
身体のバランス機能を客観的に評価するための検査です。
専用の機器の上に立っていただき、体のわずかな揺れをコンピューターで分析することで、
平衡感覚の異常やめまいの原因となる疾患の特定に役立てます。
定期的に行うことで平衡機能の回復過程を確認することもできます。
4.血液検査
貧血の有無やその程度、また止血機能など、めまいに関連する項目を調べます
5.vHIT(ビデオヘッドインパルス検査)
vHITは、内耳の前庭機能を評価するための検査です。
頭を素早く動かした際の眼球の反応を測定し、左右別々に三半規管の働きを調べることができます。
短時間で行える非侵襲的な検査で、めまいの原因診断に非常に有効です。
6.MRI
MRI検査は、脳や内耳の状態を詳しく調べ、脳梗塞・腫瘍・小脳や脳幹の異常など、重い病気の有無を確認するために行います。
ただし、めまいの原因や症状の経過、診察やほかの検査結果から必要と判断された場合にお勧めします。
耳が原因か脳が原因かを見極め、適切な治療方針を決めるための重要な検査です。
当院の
めまい診療に対する方針
めまいは日常生活に大きな支障をきたし、「この症状はいつ治るのか」「突然発症したらどうすればいいのか」など、多くの不安を感じられることでしょう。当院では、詳細な検査によってめまいの原因を特定し、患者様にわかりやすく説明することを大切にしています。原因が明らかになれば、それに応じた適切な治療計画をご提案します。
また、通院の負担を減らすことも治療の一部と考えています。当院は、伏見区の中心部、竹田駅・伏見駅から徒歩9分にあり、早期からのめまいリハビリテーションを重視しており、これにより症状の改善を早め、薬物療法への依存度を下げることを目標としています。
めまいでお困りの方は、どうぞ遠慮なくご相談ください。一人ひとりの症状に合わせた治療アプローチで、めまいのない快適な生活を取り戻すお手伝いをいたします。当院では専門のスタッフによるめまいリハビリ指導の時間を設けております。ご希望の方はお気軽に受付スタッフにお声がけください。